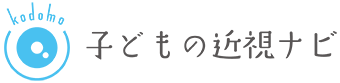子どもの将来をスマホアイから守るためのチェックポイント

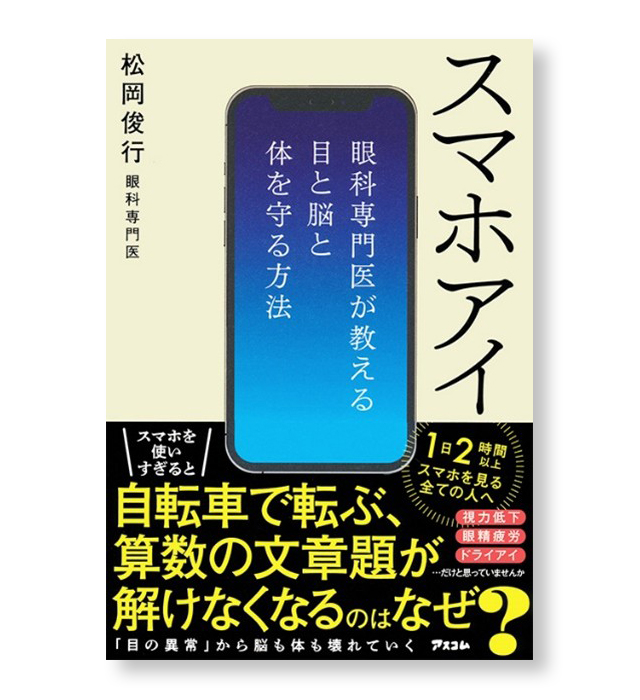
スマホアイの兆候を見逃さない
-
スマホアイになった子どもの行動や症状には次のようなものがあげられます。
・目の様子がおかしい
・視力検査で受診を指示されたが怠っている
・メガネが合っていない様子
・運動や勉強は得意なのに球技や音読が苦手
スマホアイが関係していると思われる症状の代表例として挙げられるのが、眼精疲労やドライアイ、内斜視などがあります。内斜視になるとどちらか一方目が内側に不自然に寄るという症状が表れます。お子さんと目を合わせるとすぐに気がつくものです。また、眼精疲労で起こる症状に眼瞼痙攣があります。瞼がぴくぴくとしますので、これもすぐにわかる症状といえます。また、ドライアイをはじめ、目にトラブルが発生すると目やにが多くなったり、眩しがる、目を細めてみる、目をよくこするといった兆候が見られるようになります。日ごろからお子さんと目を合わせいて話す機会を増やすことでお子さんをスマホアイから守ってあげるようにしましょう。
小学校や中学校では定期的に視力検査をしていますので、問題があれば眼科検診を勧めますが、痛みや苦痛が伴わないことが多いため、そのまま放置しているケースが少なくはないようです。
現在の視力検査では、ランドルト環と呼ばれる「C」型マークの向きで検査していますが、その際に0.3、0.7、1.0の3つの指標のみで行われています。見え方はAが1.0、Bが0.7~0.9、Cが0.3~0.6、そしてDが0.2以下の4段階で表示されています。Aは全く問題ありませんが、C、Dは眼科医の受診が必要となります。問題はBです。これに関しては受診した方がいいと判断する眼科医もいるという程度の扱いでしたが、スマホアイのことを考えると一度しっかりと検査してもらった方がいいレベルです。
足が速くて運動神経がよかったのに、球技が苦手になってきたというのもスマホアイが起因していることが少なくないようです。野球やドッジボールなどで投げるのは上手なのに取るのが苦手、サッカーボールを蹴ろうとしたら空振りすることがあるというのは、スマホのやりすぎで両眼視機能が衰え遠近感が鈍ったからと考えられるのです。いうまでもなく、日常生活にも影響を及ぼします。お子さんが物をうまくつかめない、階段の上り下りの足の運びに違和感があるようでしたらスマホアイを疑ってみてください。
さらに、スマホアイが影響して音読がスムーズにいかないという報告もあります。これは、両眼視機能が衰え、行を飛ばして読んでしまったり、どこを読んでいるかわからなくなってしまうからというわけです。こうした症状は視力が1.5、あるいは、2.0の視力の持ち主であろうとあらわれますから油断できません。文章がうまく読めないことが起因して、算数の成績が落ちるという例もあります。算数そのものは得意なのに、文章がうまく読めずに集中力が欠け、読むだけで疲れてしまい学習の効率が悪くなってしまうのです。
もはや、スマホアイが原因で本を読むのが嫌いになる、勉強そのものが嫌になるといったことにもなりかねません。小学生のお子さんなら宿題で音読がありますので、耳を傾けてそうした症状がないかをチェックしておきたいところです。また、高学年のお子さんに対しては一緒に教科書や新聞、雑誌などを読むなどの時間を作るといいでしょう。
スマホアイにはもっと恐ろしい側面があることもわかっています。それがスマホ依存症という病気です。これはアルコール依存症や先ごろメジャーリーグの大谷選手の通訳が陥ったギャンブル依存症と全く同じもので、それを治すにはプロの医療スタッフのもと、多くの時間と本人の忍耐を持って臨まなければならないという途方もない時間と治療が不可欠となります。とりわけ子どもの脳は発達しきっていませんので、大人に比べて我慢がしにくい傾向にあることから依存症に陥りやすいので注意が必要です。
スマホでゲームなどを楽しむと脳内にはドーパミンという快楽物質が放出されます。すると中枢神経が興奮し、それが「快感・喜び」につながります。こうした状況はストレス解消など私たちの生活には必要なことでもあります。しかし、それが長時間、あるいは、頻繁なこととなるとドーパミンが大量に分泌することによって脳が興奮し、さらなる報酬を求め、これを繰り返すことで、脳内の報酬系統が強化され、それなしでは生きていけない依存症に陥ってしまうのです。さらに、その依存症はスマホだけに限らず何に対しても依存しやすくなってしまうと考えられています。さらに、ドーパミンが過剰になると脳内ホルモンのバランスが乱れ我慢ができにくい、つまり、切れやすい精神状態にもなってしまうことが懸念されます。
そもそもドーパミンは「闘う」を後押しする物質です。それに対して「逃げる」選択を後押しする物質のセロトニンという神経伝達物質があります。この二つがバランスを保つことで私たちは正常に物事を判断しているのです。しかし、スマホによってドーパミンが過剰になるとバランスが崩れハイな状態となり衝動的な行動を起こしやすくなってしまうのです。
子どもが反抗期時期にある時は、切れやすいのは仕方ないことと見逃すこともありそうですし、スマホを強制的に取り上げたことで一時的に興奮しているのだと判断してしまうこともあるかもしれません。しかし、そもそもの原因がスマホの使い過ぎでそういう状態に陥っている可能性もあるので、その点もしっかりとチェックするようにしましょう。
次回はスマホアイの治療法について紹介します。
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその①
大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大事な子どもの視力を守る先行投資」
- 最新の治療に目を向けていただきたい 今年7月に放映された人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS/TBS系)で取り上げられた眼科医の大野京子先生(東京医科歯科大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長)は、アジア太平洋眼科学会で“Queen of Myopia(近視医療の女王)”として表彰された、小児の近視治療のリーダーのひとりです。大野先生は「子どもたちの大事な視力を守るために

レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
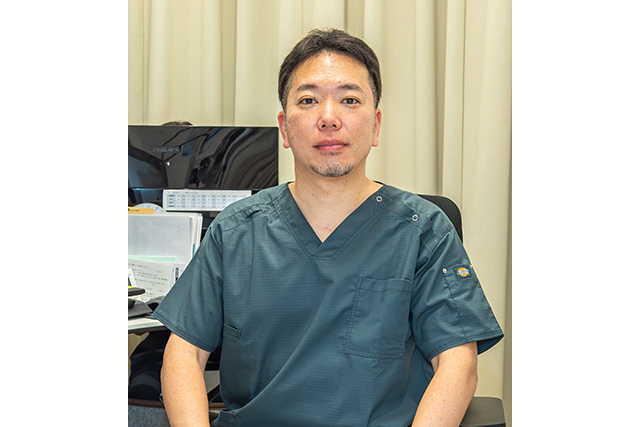
関連記事
1日2時間以上スマホを見ている子どもの脳に障害の恐れ
自転車で転ぶ、算数の文章問題が解けない、子どもの「スマホアイ」に要注意
- スマホの長時間の使用が子どもの視力に影響を与えているということは、さまざまな先生が警鐘を鳴らしはじめており、「子どもの近視ナビ」でも何度か記事を取り扱いました。『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)を出版した江坂まつおか眼科の松岡俊行院長は、「スマホの見過ぎによって『スマホアイ』といった状態になってしまうとさまざまな危険性がある」と警鐘をならしていま

スマホなどの見過ぎで起きるスマホアイを防ぐために
眼科医がすすめる目を守るためのスマホの“ある設定”
- スマホの見過ぎでおきる「スマホアイ」によって、子どもの目や脳には大きな悪影響を受けます。とはいえ、スマホを完全に禁止するのは難しいでしょう。では、どうすればいいのか。『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)の著者である江坂まつおか眼科の松岡俊行院長にお聞きします。自然に目をスマホアイから守ってくれる便利なスマホ設定スマホの画面に