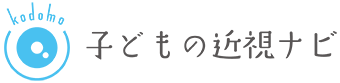スマホなどの見過ぎで起きるスマホアイを防ぐために

自然に目をスマホアイから守ってくれる便利なスマホ設定
スマホの画面に集中していると姿勢がうつむきかげんになりますから、猫背になり、画面をのぞき込むようになっています。この姿勢では、目とスマホが面の距離が近づきすぎですし、寄り目の状態になってしまっているため、目はいたく疲弊してしまいます。まして、腕の短い子どもがスマホアイにならないわけがありません。スマホを見る時の距離は30センチ以上を保つようにすることをお勧めします。さらに、ソファやベッドに寝転がってスマホを見るのもよくありません。寝ながらではスマホと目の距離が座っているときよりずっと短くなることと、横になっていることでスマホに近い方の目ばかりを酷使することになり、両目の負担が偏ることから視力差が生じる原因ともなりますので注意が必要です。また、暗い中で明るいスマホ画面を見ると目は驚くほど酷使されます。布団にもぐってのスマホ使用はやめるに限ります。
スマホと目の距離が短いから危険とはいっても、距離を離して使用するのは、現実的でないというのも事実です。そこでお勧めは、スマホ文字表示を出来るだけ大きく設定するということです。文字が小さいと文字を読もうと画面に近づけてしまいますので文字サイズを大きくすることで、そのリスクが多少なりとも軽減できることになります。
よくあるのが部屋が暗いのに画面が明るい、明るい部屋でスマホを操作しているのに、その画面が暗いという使用法。明暗の差は、目にとって大きな負担となります。スマホ画面の明るさは周囲の明るさに合わせるといいでしょう。
スマホアイの「20・20・20ルール」という予防と改善方法
スマホ画面を見る時間が長いのは、仮に姿勢が良くしたり、スマホ文字や明るさを調整したといっても目にとっての負担はそれほど軽減できるものではありません。やはりスマホを見る時間を短くすることがスマホアイの一番の予防法です。しかし、スマホ時間を短くするのはなかなか難しいもの。そこで習慣付けたいのが、目を疲労から守る「20・20・20・ルール」です。20・20・20ルールとは、20分間スマホを見たら、20秒間、20フィート(約6メートル)離れたところを眺めるという予防法です。これは米国眼科学科会議が推奨している目の休憩ルールで、これを続けることで目の負担が軽減したという報告もある予防方法です。
スマホ画面から目を離し、6メートル先を見ようとピントを調整することで、凝り固まった筋肉の緊張がほぐされ目がリラックスし、さらに目から送られてくる情報の処理に追われた能もひと休みできるのです。ぜひお試しください。
スマホアイに低濃度アトロピンなどの近視予防習慣
目に必要なことのひとつに肌のお手入れ同様の潤いがあります。目にとっても肌にとっても乾燥はダメージとなりやすく、とりわけ冬場の大気と暖房使用による乾燥は大敵となります。そうした環境には加湿器を多用することでスマホアイやドライアイの予防となります。また、直接目に潤いを施す目薬も効果的です。一般的には大人であれば3時間に1回、子どもは朝の登校時と就寝前の2回くらいで十分ですが、スマホアイに対しては20分に一度、スマホ休憩時間を設け、その都度目薬をさすということを習慣づけるといいでしょう。
目の見え方が一人ひとり違うように、スマホアイの程度や進行にも個人差があることから、すべての人が生活習慣やスマホ設定などだけで視力の低下を抑止することはできません。
スマホアイによって近視になると眼科医院の手助けが必要になります。一般的に近視になるとメガネで目を矯正することになりますが、実はそれでは近視を治療したことにはなりません。あくまでもメガネで視力を矯正したに過ぎないのです。とりわけお子様の近視は矯正ではなく、しっかりと治療することをお勧めします。
私の医院ではオルソケラトロジーという角膜矯正療法を取り入れています。これは、ウエストを細く保つコルセットのような矯正方法とイメージ的には同じで、就寝中にコンタクトレンズを装着することで、角膜に圧をかけてピントが合うように矯正するというもので、日中は裸眼で快適に過ごせるという治療方法です。
さらに私がお勧めしているのが、近視抑制治療です。低濃度アトロピンを点眼して近視の進行を抑制するというものです。低濃度アトロピン点眼という低濃度アトロピンを使った近視抑制治療法で、対象は軽度から中等度の近視がある6~12歳のお子さまです。毎日就寝前に一滴、低濃度アトロピン点眼を点眼するだけで、近視の進行を平均60%軽減させることができると期待されています。また、低濃度であるため瞳孔が開きすぎてまぶしさを敏感に感じ取ってしまうという副作用もほとんどありません。
低濃度アトロピン点眼は少なくとも2年間の継続的治療が望まれますが、これを点眼することで近方、遠方を見るときの調節機能にほとんど影響なく、快適に日常生活を送ることができるうえ、就寝前の一滴の点眼のみという負担の少ない治療法です。
近視予防治療として、もう1つ有効なのが、オルソケラトロジーです。こちらは、近視抑制のための特殊なコンタクトレンズを入れるというもので、低濃度アトロピン点眼と併用すると、近視予防効果が高まると言われています。スマホでお子様の近視が気になるという方は、眼科医院に相談してみてください。
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
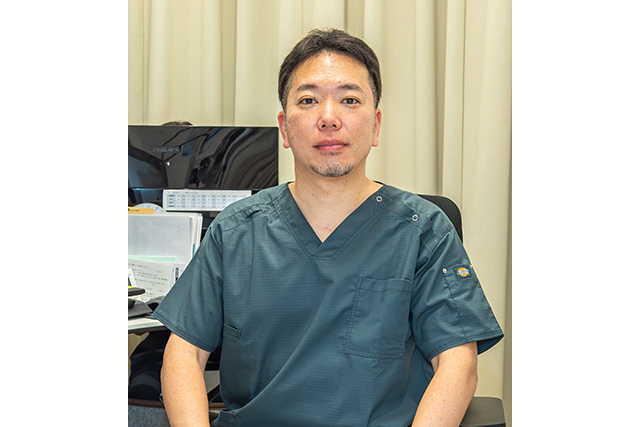
近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその①
大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大事な子どもの視力を守る先行投資」
- 最新の治療に目を向けていただきたい 今年7月に放映された人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS/TBS系)で取り上げられた眼科医の大野京子先生(東京医科歯科大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長)は、アジア太平洋眼科学会で“Queen of Myopia(近視医療の女王)”として表彰された、小児の近視治療のリーダーのひとりです。大野先生は「子どもたちの大事な視力を守るために

関連記事
1日2時間以上スマホを見ている子どもの脳に障害の恐れ
自転車で転ぶ、算数の文章問題が解けない、子どもの「スマホアイ」に要注意
- スマホの長時間の使用が子どもの視力に影響を与えているということは、さまざまな先生が警鐘を鳴らしはじめており、「子どもの近視ナビ」でも何度か記事を取り扱いました。『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)を出版した江坂まつおか眼科の松岡俊行院長は、「スマホの見過ぎによって『スマホアイ』といった状態になってしまうとさまざまな危険性がある」と警鐘をならしていま

子どもの将来をスマホアイから守るためのチェックポイント
「スマホアイ」を見逃さないための4つのポイント
- 子どもたちの目と脳に障害をきたす「スマホアイ」。今回は、そうならないためのチェック方法を『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)の著者である江坂まつおか眼科の松岡俊行院長にお聞きします。スマホアイの兆候を見逃さないスマホアイになった子どもの行動や症状には次のよ