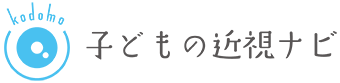「やめなさい」は一番の悪手!
ポイントは、「命令」ではなく「質問」
――うちの子どももそうなんですが、ゲームとか、今はスマートフォンなどでYouTubeとか、長時間、観ているので、「目が悪くなるので、やめなさい」というのですが、なかなかやめないんですよね。 ちゃんとやめるお子さんと、そうではないお子さんには、決定的な違いがあって、それは親の声掛けの仕方なんです。よくやってしまいがちなのが、「やめなさい」とか、「いつまでやっているの?」「いい加減にしなさい」という命令です。これはあまりよくありません。
ちゃんとやめるお子さんと、そうではないお子さんには、決定的な違いがあって、それは親の声掛けの仕方なんです。よくやってしまいがちなのが、「やめなさい」とか、「いつまでやっているの?」「いい加減にしなさい」という命令です。これはあまりよくありません。心理学の専門用語で心理的リアクタンスっていうんですけど、リアクタンスって抵抗っていう意味なんです。例えば「この箱を絶対開けないで」って言ったらどうですか。開けたくなりますよね。人間って悲しいもので、命令されると、その逆をやりたくなってしまう。これが脳の性質なんです。なので、ゲームをやめなさいっていうのは、油に火に油を注ぐようなもので、逆にもっとやりたくなってしまいます。
――なるほど、確かに「やめなさい」と注意しがちですね。ではどうすればよいのでしょうか。
大切なのは、「命令」ではなく、「質問」をすることです。
 一番ですね有効な方法としては、「あと何分で止めるの?」っていうふうに聞くことなんです。子供というのは年齢によっても違うんですけど、「もう30分やったらやめる」とか、「1時間やったらやめる」と言います。そうすると、不思議とやめる確率が高まって驚くかもしれません。通常、子どもは、「やめなさい」と言っても、今は「ゲームをやっている」「TVなどを観ている」わけですから、やめるイメージは到底できません。
一番ですね有効な方法としては、「あと何分で止めるの?」っていうふうに聞くことなんです。子供というのは年齢によっても違うんですけど、「もう30分やったらやめる」とか、「1時間やったらやめる」と言います。そうすると、不思議とやめる確率が高まって驚くかもしれません。通常、子どもは、「やめなさい」と言っても、今は「ゲームをやっている」「TVなどを観ている」わけですから、やめるイメージは到底できません。
ですが、「いつやめるの?」と聞いた瞬間に、いつやめようかなと子どもなりに想像しはじめます。脳というのはイメージが浮かんだ瞬間に、その行動を実行しようとする不思議な性質があります。これを「コミットメント効果」といいます。親が決めたことではなく、自分で決めたほうが行動しやすくなるんです。なので「あと30分でやめなさい」と言うのは、あまり効果がありません。
話すときは、必ず目を見て話させる
――なるほど。でも、話しかけても子どもが聞かないことがありますよね。生返事で返すというか。それだとあまり意味がないですね。ゲームやTVの映像が頭を支配しているので、やめるイメージが頭に浮かびません。必ず、一度、ストップしてもらってから、こちらに体と顔を向けた状態で話すのがポイントです。言葉で話しかけても振り向かないときは、肩を軽くぽんぽんするなど、身体的接触で気づかせるというのもよいでしょう。
はじめる前にしっかりと約束をするのもいいと思います。
それでも時間通りにやめないときは、子どもの尊敬する人の名前を挙げるのもよいでしょう。例えば「大谷選手だったらどうすると思う? そんなゲームばっかりやっているかな?」と、これもきちっと一度、今やっていることをやめさせてから話してみてください。
有名人じゃなくても、兄弟とか、身近な人の名前を出してもいいでしょう。
もう1つ、効果的なのは、終わる時間に音楽を流すことです。好きな曲がかかると、脳はドーパミンが出て、切り替えのスイッチが働きやすくなります。
買い物をしているとき蛍の光がかかると、「あっもう閉店だ」とどこかそわそわした気持ちになりますよね。音楽には、気持ちのスイッチを切り替える力があるので、効果的な方法だといえると思います。
――ありがとうございます。僕も子どもに試してみます。
【今回お話を聞いた方】
西剛志(にし・たけゆき)
 脳科学者。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、才能を引き出す方法を紹介し、企業から教育者、高齢者、主婦をなど含めてこれまで3万人以上に講演会を行う。「ザ!世界仰天ニュース」「モーニングショー」「カズレーザーと学ぶ。」などテレビ出演も多数。2019年、『脳科学的に正しい 一流の子育てQ&A』(ダイヤモンド社)で著者デビュー。『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(アスコム)が20万部のベストセラーに。
脳科学者。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、才能を引き出す方法を紹介し、企業から教育者、高齢者、主婦をなど含めてこれまで3万人以上に講演会を行う。「ザ!世界仰天ニュース」「モーニングショー」「カズレーザーと学ぶ。」などテレビ出演も多数。2019年、『脳科学的に正しい 一流の子育てQ&A』(ダイヤモンド社)で著者デビュー。『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(アスコム)が20万部のベストセラーに。
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
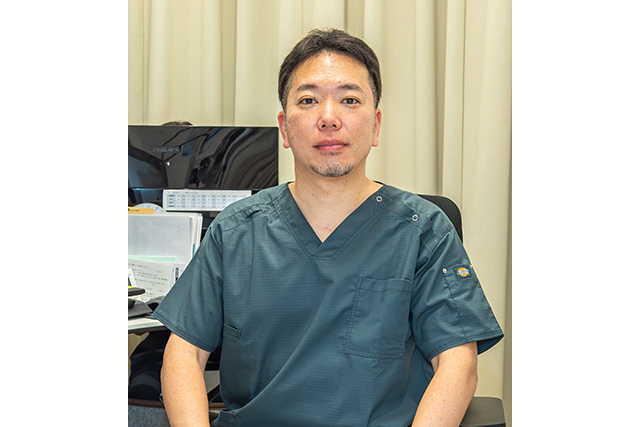
日本でもクリニックで受けられるように
子どもの眼を守るために知っておきたい 話題のレッドライトについて
- 近年注目されている視力改善の新しいアプローチの一つであるレッドライト療法(赤色光療法)。特に近視の進行を抑える可能性があるとされており、「子どもの近視ナビ」でも、日本でレッドライト研究の第一人者といわれる東京医科歯科大学眼科学教室教授の大野京子先生に1年前に取材をさせていただき、紹介させていただきました。 関連記事:特別インタビューその①大野京子医師「近視の進行抑制治療

関連記事
スマホなどの見過ぎで起きるスマホアイを防ぐために
眼科医がすすめる目を守るためのスマホの“ある設定”
- スマホの見過ぎでおきる「スマホアイ」によって、子どもの目や脳には大きな悪影響を受けます。とはいえ、スマホを完全に禁止するのは難しいでしょう。では、どうすればいいのか。『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)の著者である江坂まつおか眼科の松岡俊行院長にお聞きします。自然に目をスマホアイから守ってくれる便利なスマホ設定スマホの画面に

「外出」が「ご褒美」になるように仕向けよう
先生教えて!子どもが外で遊ばないけどどうしたらいい?
- 当サイトでも何度か取り上げたように、世界共通で認識・信頼されている近視の原因には、「外遊び(屋外活動)」の減少があります。子どもの近視が深刻な問題となっているシンガポールでは、近視の進行を抑えるために、学校教育のカリキュラムに屋外活動の時間を組み込むなど、外遊びを推進する取り組みを行っているといいます。また、日本でも、眼科医会がホームページで、1日2時間外で遊ぶことの大切さをうたっていま