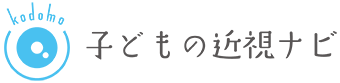「外出」が「ご褒美」になるように仕向けよう
しかし、「外で遊んだら?」と言ってもなかなか、外で遊ばないというお子さんも多いのではないでしょうか。そこで、前回、「脳科学者に聞く、ゲームやTVの長時間の使用を止めさせる方法」(前回記事リンクに飛ぶ)でお話を聞いた脳科学者の西剛志先生に外遊びへ子どもを促す方法を聞いてみました。
外遊びが嫌いな子は外=嫌な場所になっている可能性が
――遊ぶといっても、部屋の中でゲームをしたり、漫画を読んだり。うちの子もそうなんですけど、なかなか、外で遊ばなくて、それが近視を助長しているような気がして
確か、外遊びの近視抑制って、外に出ることが大事だったりしますよね?
――そうですね。日陰でもいいので、太陽光の中に含まれる、バイオレットライトを浴びることが大切だと言われています
 なるほど。なら、外に出るということを基点にして考えてみると、1つは、子どもが好きなものを利用するという手があります。外に出たがらない子どもというのは、「外」=「不快」な場所と感じているケースが少なくありません。ですから、「外」=「快感」を与えてくれる場所という意識づけがまず大切です。
なるほど。なら、外に出るということを基点にして考えてみると、1つは、子どもが好きなものを利用するという手があります。外に出たがらない子どもというのは、「外」=「不快」な場所と感じているケースが少なくありません。ですから、「外」=「快感」を与えてくれる場所という意識づけがまず大切です。私の子どもは、電車が好きなので、「電車を見に行こう」とよく外に連れ出していますが、なんでもいいと思います。好きなキャラクターに会いにいく、とか動物が好きな子なら動物園に行くとか。そういったことから初めてください。
また、子どもは、歩くのが嫌いで外出しないという子もいる。ですが、結構自転車に乗るのが好きな子もいるんですよね。なので、自転車が好きな子は、新しい自転車を買ってあげるというのも1つの方法かと思います。
大人と子どもでは、感じる時間が違う
――なるほど。なら、僕も遊園地とか、頻繁に連れて行ってみようかな
 ただ、気をつけないといけないのは、子どもの性格は大きく内向型と外向型の2種類に分けられていることです。外向型のお子さんは外に出るのが好きなんですが、内向型のお子さんは、あまり好きではありません。特に、人混みを苦手にしているケースが多いので、できれば人混みが少ないところのほうがよいでしょう。
ただ、気をつけないといけないのは、子どもの性格は大きく内向型と外向型の2種類に分けられていることです。外向型のお子さんは外に出るのが好きなんですが、内向型のお子さんは、あまり好きではありません。特に、人混みを苦手にしているケースが多いので、できれば人混みが少ないところのほうがよいでしょう。
よく、親がよかれと思って、人気のレストランなどに子どもと一緒に並んでいるところを観ますが、あれは、「外」=「痛み」と思わせる可能性があります。
まず、子どもは大人よりも、我慢をするのが苦手です。我慢をするというのは、脳のなかでも前頭葉が主に担っているのですが、前頭葉は、28歳まで成長するんです。子どもはまだ未発達の場合が多く、長時間の我慢がストレスに感じてしまうのです。例えその後にご褒美が待っていたとしても、「外」=「痛み」になってしまう可能性が高いですね。
また、子どもと大人を比べると、大人のほうが時間を長く感じてしまうことがわかっています。年をとってくると1週間ってあという間なのに、子どものときって夏休みを永遠のように感じられませんでしたか?これは「代謝バイアス」っていう時間に関するバイアスなんですけど代謝が高いと、同じ期間でも時間が長く感じるようになるんです。なので、代謝が高い子どもは、大人よりも時間を長く感じやすいため、ちょっとした待ち時間でも苦痛に感じていることがあるというのは、覚えておいた方がいいかもしれません。
とにかく「外」=「快感」なものなんだよと、インプットさせることが大切です。
――子どもを楽しませようと思うのが逆効果になっていることもあるんですね。どうも今回はありがとうございました。
【今回お話を聞いた方】
西剛志(にし・たけゆき)
 脳科学者。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、才能を引き出す方法を紹介し、企業から教育者、高齢者、主婦をなど含めてこれまで3万人以上に講演会を行う。「ザ!世界仰天ニュース」「モーニングショー」「カズレーザーと学ぶ。」などテレビ出演も多数。2019年、『脳科学的に正しい 一流の子育てQ&A』(ダイヤモンド社)で著者デビュー。『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(アスコム)が20万部のベストセラーに。
脳科学者。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、才能を引き出す方法を紹介し、企業から教育者、高齢者、主婦をなど含めてこれまで3万人以上に講演会を行う。「ザ!世界仰天ニュース」「モーニングショー」「カズレーザーと学ぶ。」などテレビ出演も多数。2019年、『脳科学的に正しい 一流の子育てQ&A』(ダイヤモンド社)で著者デビュー。『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(アスコム)が20万部のベストセラーに。
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
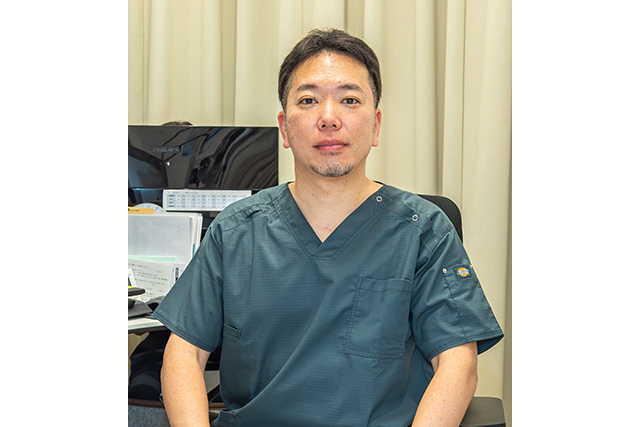
日本でもクリニックで受けられるように
子どもの眼を守るために知っておきたい 話題のレッドライトについて
- 近年注目されている視力改善の新しいアプローチの一つであるレッドライト療法(赤色光療法)。特に近視の進行を抑える可能性があるとされており、「子どもの近視ナビ」でも、日本でレッドライト研究の第一人者といわれる東京医科歯科大学眼科学教室教授の大野京子先生に1年前に取材をさせていただき、紹介させていただきました。 関連記事:特別インタビューその①大野京子医師「近視の進行抑制治療

関連記事
スマホなどの見過ぎで起きるスマホアイを防ぐために
眼科医がすすめる目を守るためのスマホの“ある設定”
- スマホの見過ぎでおきる「スマホアイ」によって、子どもの目や脳には大きな悪影響を受けます。とはいえ、スマホを完全に禁止するのは難しいでしょう。では、どうすればいいのか。『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)の著者である江坂まつおか眼科の松岡俊行院長にお聞きします。自然に目をスマホアイから守ってくれる便利なスマホ設定スマホの画面に

「やめなさい」は一番の悪手!
脳科学者に聞く、ゲームやTVの長時間の使用を止めさせる方法
- ゲームやTV、スマートフォンなどの長時間は、子どもの目に悪影響を与える。今、いろいろなメディアで語られるところです。ですが、「やめなさい」と言っても、なかなかやめないもの。さんざん怒ってやめさせてもまた、いつのまにか長時間やっている。そんなことはありませんか?そこで、今回、『脳科学的に正しい一流の子育てQ&A』(ダイヤモンド社)などの著者であり、栃木県保育協議会県南部地区保育研究会/