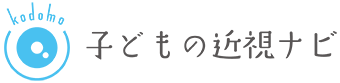放っておくと、メガネをかけても十分な視力が出なくなるケースも……

と話すのは、CS眼科クリニック院長の宇井牧子先生。子どもの眼科診療に精通する専門医です。
確かに、「うちの子、左右の視力がこんなにちがうけど、それってよくあること?」「どれくらいの差なら大丈夫なの?」「片方の目だけに負担がかかり過ぎるのではないかしら」などと心配になる気持ちもわかります。
左右の目の屈折度がちがうこと─つまり視力の差があることを、眼科では“不同視(ふどうし)”といいます。正確には、左右の屈折度の差が2D(ディオプトリー、注)以上ある状態を不同視といいます。
でも、宇井先生によれば、左右の視力がちがっても、近視の場合なら、あまり心配しなくてもよいのだとか。
「親御さんは、片方の目だけ近視が強いことをとても心配するのですが、近視であれば、ある程度の左右差があっても大丈夫です。たとえば、視力が0.5と0.1だとしたら、眼軸(目の奥行き)の長さの差でいうと0.1mmくらいの差でしかありません。そのくらいなら、正常範囲だといっていいでしょう」(宇井先生、以下同)
子どもの近視は、眼軸が伸びることによって進むことは、すでに別の記事で解説しました。視力の左右のちがいも、この眼軸の左右差によって生じるものです。
手足の長さやまぶたの形に差があるのと同じように、左右の目の眼軸の長さも差があるのがふつうであり、その左右差が埋まることはあまりなくて、どちらも成長にともなって伸びていきます。
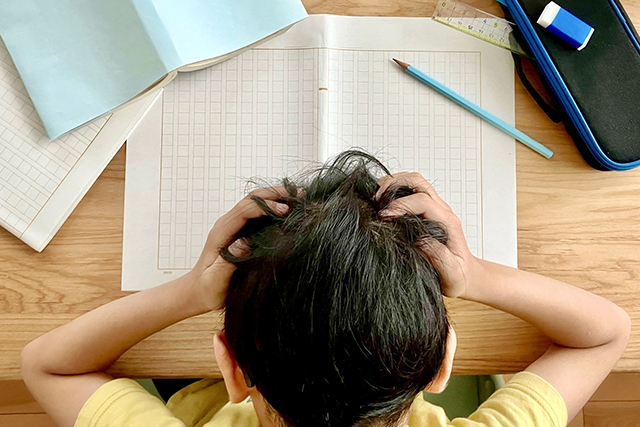
ところが、遠視がある場合は、要注意です。
「左右の目の屈折度がちがうこと─つまり視力の差があることを、眼科では“不同視(ふどうし)”といいます。子どもの不同視で問題となるのは、近視ではなくて遠視の左右差が大きい場合です。
遠視が強いほうの目は、いつもピンぼけ状態ではっきり見えないために、脳にピントの合った像を送ることができません。そのため、気づかずに放置しておくと、もう片方のピントが合いやすい目ばかりを使うようになって、遠視が強いほうは、ものを見るための脳の機能が十分に発達することができません。その結果、“不同視弱視“(視力の左右差から起こる弱視)になるケースが多いのです」
弱視というのは、なんらかの原因でものを見る機能が発達することができず、メガネをかけても十分な視力が出ない状態です。目の視機能は8歳前後までに完成するため、それまでに適切な治療ができずに弱視になってしまうと、メガネやコンタクトレンズを使っても視力が上がりません。
「遠視による不同視の治療は、ピントの合う状態でものを見ることができるように、常にメガネをかけて過ごさせることです。それでも視力が上がらない場合は、1日に数時間、視力がいいほうの目を隠して、悪いほうの目を使うようにする訓練を追加します。
せっかく治療を始めたのに、祖父母などまわりの大人が“まだ小さいのに、メガネをかけるなんてかわいそう”と口を出すようなケースが少なくないのですが、それは本末転倒です。むしろ、メガネをかけさせないことのほうが、弱視を招くことになりかねないので、その子にとってはかわいそうなのです」
8歳以降で不同視弱視が見つかり、それから治療を開始しても、視力が上がるケースもあります。しかし、やはり視力がどうしても上がらないうえに、本人にとってもいい方の目を隠す訓練がストレスになり、訓練を断念することもあります。
また、「大人でも、左右の視力の差が大きければメガネで調節してるんだから、子どもでも同じことでしょう?」と楽観的にとらえる人がいるのですが、子どもの遠視の不同視の場合、それは×。
大人の不同視─いわゆる“ガチャ目”─の場合、目が疲れやすい、ものが二重に見える、めまいや頭痛・吐き気・肩こりなどがある、ものや人との距離感がつかみにくいなどの症状をともなうことがありますがが、眼科できちんと視力を測り、メガネやコンタクトレンズを使って左右の視力を調節すると症状がやわらぐことが多いはずです。
しかし、 その“ガチャ目”は、すでに視力が完成された大人の話であり、まだ視機能が発達途上にある子どもの不同視を、同じようにとらえてはいけません。
視力の矯正や治療が必要な子どもの近視や遠視、乱視は、学校の視力検査だけでは見つけられないことも多いので、気になる症状がなくても、年に一度は眼科を受診して視力の確認をしておけば安心ですね。
注:ディオプトリー 視力矯正のためのレンズの度数の単位。数字が大きいほど、近視の度が強いレンズであることを意味する。
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
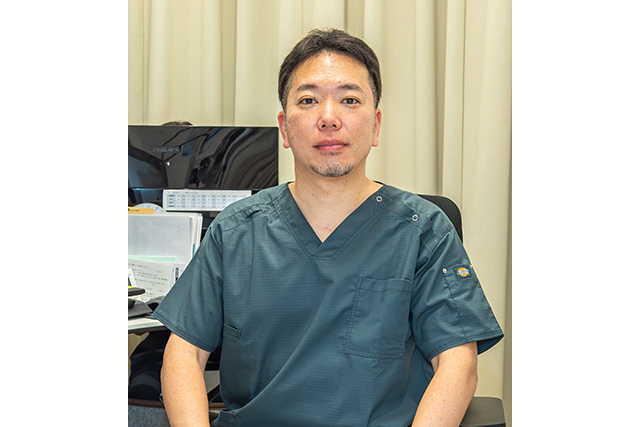
日本でもクリニックで受けられるように
子どもの眼を守るために知っておきたい 話題のレッドライトについて
- 近年注目されている視力改善の新しいアプローチの一つであるレッドライト療法(赤色光療法)。特に近視の進行を抑える可能性があるとされており、「子どもの近視ナビ」でも、日本でレッドライト研究の第一人者といわれる東京医科歯科大学眼科学教室教授の大野京子先生に1年前に取材をさせていただき、紹介させていただきました。 関連記事:特別インタビューその①大野京子医師「近視の進行抑制治療

関連記事
レベルが高い眼科医院を見分ける方法とは
「いい眼科」を選ぶためのたった1つのポイント
- “視能訓練士”学校の視力検査を受けた子どもが悪い結果を持ってきたり、遠くのものを見えにくそうにしていたりしたら、ドキッとしてしまいますよね。子どもの目に違和感を覚えたら、一刻も早く眼科医を受診したいはずです。でも、焦ってスマホで検索してみても、家の近所には思っていた以上にたくさんの眼科専門医があることがわかりますよね。ホームページを一つ一つ見てみると、どこの

スマホによる寄り目の固定化はどうやって防ぐ?
いま急増中!スマホの使い過ぎで斜視に?!
- 子どもがスマホを日常的に使う場面が増え、小学校高学年では、6割以上の子どもがスマホを持っているという報告もあります。スマホの普及にともなって、目の疲れや近視、乱視などが増えていますが、もうひとつ注意したい目の機能の異常があります。それが「スマホ内斜視」です。 CS眼科クリニックの宇井牧子先生に、その実態をうかがってみました。 「最近、スマホに