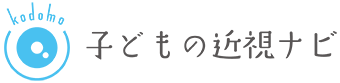子どもと読む目の絵本シリーズ
『メガネをかけたらどうなるの?』
(ほるぷ出版)
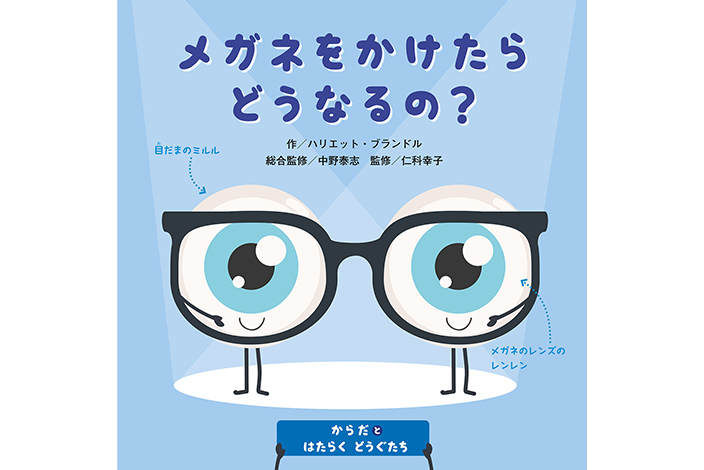
『メガネをかけたらどうなるの?』は、メガネだけでなく歯の矯正器具や補聴器、義肢など、何か困ったことがあるときに、体と一緒に働いてくれる道具たちを紹介する絵本シリーズの1冊。今回ご紹介する絵本も、メガネを使う人の気持ちや立場を想像しながら、メガネをかけることへの理解を深めることができる本となっています。
この本では、目玉の「ミルミル」とメガネのレンズの「レンレン」がガイドになって、目のしくみやものを見るメカニズム、見えにくくなったらどうするのか、メガネをかけることで見え方がどう変わるのか、そしてメガネのしくみや取り扱い方などを紹介していきます。最後のページには、コンタクトレンズの説明もあります。
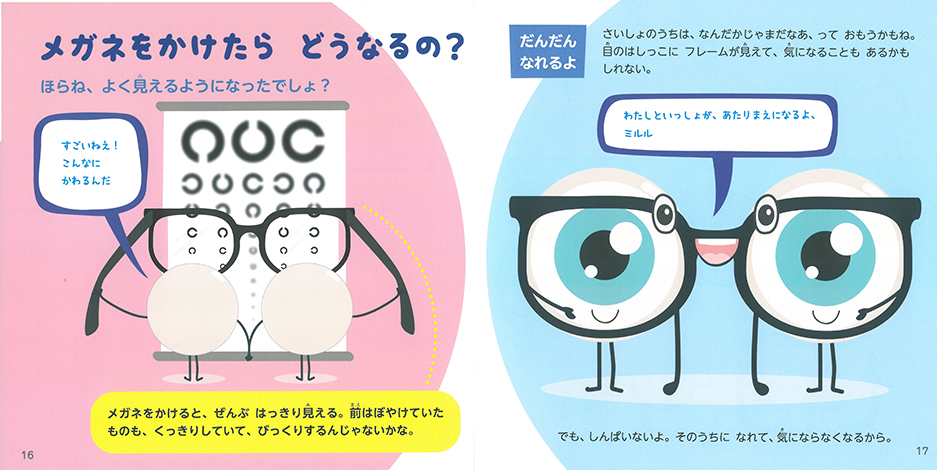
小児眼科の専門医が内容を監修しているので、メガネが「見る力」を育て、「見ること」を助ける道具であることが医学的にも正確に説明されています。
小さい子どもにとって、“はじめてメガネをかける”というイベントは、大人が考える以上にドキドキするもの。メガネをかけて学校に行くのが恥ずかしかったり、まわりの友だちの目が気になったりする子もいます。
でも、黒板が見えないときだけメガネをかけるのではなく、遠視などのように、ずっとかけていないと視力が低下していく場合もあります。メガネが必要になったら、“なぜかけるのか”を必ずお子さんにもきちんと説明してあげてほしいのです。
実は、小さいお子さんに読み聞かせる絵本としては、ややむずかしい内容です。でも、小学校高学年以上のお子さんが自分で読むとき、またお母さん、お父さんが“メガネをかけるとどうなるのか”“何のためにかけるのか”をまずご自分が理解して、お子さんにわかるように説明するときには、とても役に立つと思います。
メガネはおもちゃではなく、大切な道具であることを本人に説明するときはもちろん、兄弟姉妹や幼稚園・学校の友だちがメガネをかけ始めたときなどにも、おすすめの1冊です。
監修/宇井牧子先生(CS眼科クリニック院長)
参考文献/
からだとはたらくどうぐたち
『メガネをかけたらどうなるの?』
ハリエット・ブランドル作/中野泰志 総合監修・仁科幸子 監修
(ほるぷ出版、2022年)
- 注目記事 →↓
- 子どもの眼を守るために知っておきたい
話題のレッドライトについて
人気記事
近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその①
大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大事な子どもの視力を守る先行投資」
- 最新の治療に目を向けていただきたい 今年7月に放映された人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS/TBS系)で取り上げられた眼科医の大野京子先生(東京医科歯科大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長)は、アジア太平洋眼科学会で“Queen of Myopia(近視医療の女王)”として表彰された、小児の近視治療のリーダーのひとりです。大野先生は「子どもたちの大事な視力を守るために

レッドライト療法の現場から①
眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?
- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大
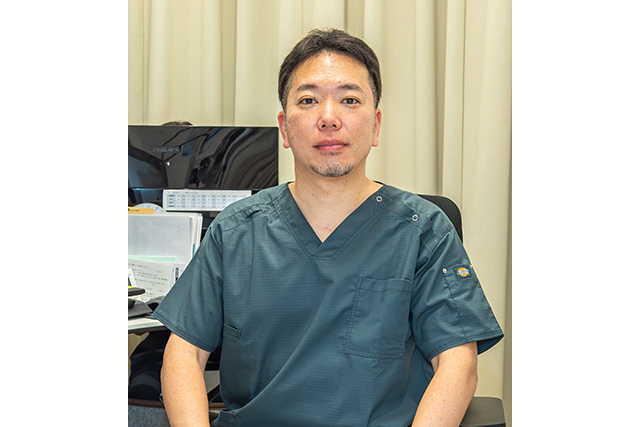
関連記事
小児のコンタクトレンズ
子どもがコンタクトレンズを入れても大丈夫?何歳から?ソフトレンズorハードレンズ?
- できればメガネはかけたくない近視や乱視などが進んで視力矯正が必要だけれど、「できればメガネはかけたくない」となると、コンタクトレンズを検討することになりますが、―――そもそも、子どもが使っていいものなの?―――何歳ぐらいからなら使えるの?―――ハードとソフトってどっちがいい?など、わからないことが多いですよね。

【子どもの近視治療のいまを語るVol.1】CS眼科クリニック 宇井 牧子院長 〈第1回〉
子どもの診療は未来を守る仕事。やりがいのある毎日が待っています!
- 小児の近視進行抑制治療の急速な進歩この数年で、近視の進行抑制治療が大きく変化していることは、先生方もよくご存知のことと思います。特に、COVID-19の感染拡大に伴うオンライン授業や外遊び時間の短縮の影響は大きく、アジア諸国では小児の近視の増加と低年齢化が顕著であり、大きな問題となっています。近視の発症が早いほど強度近視のリスクが高く、強度近視に陥る可能性があるよ